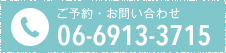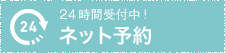むし歯治療後に気をつけたい「2次う蝕」とは?
2024年12月23日
歯科治療を受けた後も、再度むし歯が発生することを「2次う蝕」といいます。2次う蝕は、治療した歯の詰め物や被せ物の隙間からむし歯菌が侵入し、再びむし歯が進行する状態です。今回は、2次う蝕の主な原因や予防方法についてご紹介します。
- 2次う蝕の原因
2次う蝕の原因には、主に以下の3つが挙げられます。
・補綴物の劣化
詰め物や被せ物(補綴物)は、時間の経過とともに劣化していきます。口腔内は温度や湿度が変動しやすく、また食べ物や飲み物の酸や糖分の影響を受けやすいため、補綴物の接着部分が少しずつ剥がれて隙間が生じることがあります。この隙間からむし歯菌が侵入し、2次う蝕が進行する原因となります。特に、保険診療で用いられる金属製の補綴物は劣化しやすい傾向があり、長期間の使用で破損したり隙間ができやすくなります。
・治療精度の低さ
歯科治療の精度が低い場合、詰め物や被せ物が歯にぴったりとフィットせず、わずかな隙間ができてしまいます。この隙間にはむし歯の原因となる細菌が入り込みやすく、2次う蝕のリスクが高まります。
・不十分なプラークコントロール
日々のセルフケアでプラークコントロールが不十分であると、補綴物の周囲にむし歯の原因となる細菌が増え、再度むし歯が発生するリスクが高まります。特に補綴物の周囲は汚れがたまりやすく、歯磨きが行き届かないことがあります。
- 2次う蝕を予防するためには
2次う蝕の予防には、以下のようなポイントを心がけることが大切です。
・定期的な歯科検診
詰め物や被せ物の下でむし歯が再発している場合、肉眼ではむし歯を発見できません。定期検診を受けてレントゲン検査を行えば、補綴物の状態やむし歯の有無を早期に確認できます。劣化した補綴物は、早めに修復や交換を行うことで、2次う蝕のリスクを抑えることができます。
・高精度な治療を受ける
精度の高い補綴物を装着することで隙間が生じにくくなり、2次う蝕の予防につながります。補綴物にはセラミックやジルコニアなど、劣化しにくい素材を検討すると良いでしょう。
・毎日のプラークコントロール
歯ブラシだけでなく歯間ブラシやデンタルフロスを活用して、補綴物の周りも含めたプラークコントロールを徹底することが必要です。毎日念入りにケアを行いましょう。
- まとめ
2次う蝕は補綴物の劣化や治療精度の低さ、不十分なプラークコントロールが主な原因となります。日頃から定期的な検診や適切なプラークコントロールを心がけ、2次う蝕の発生を防ぎましょう。